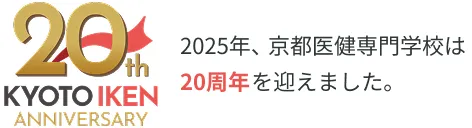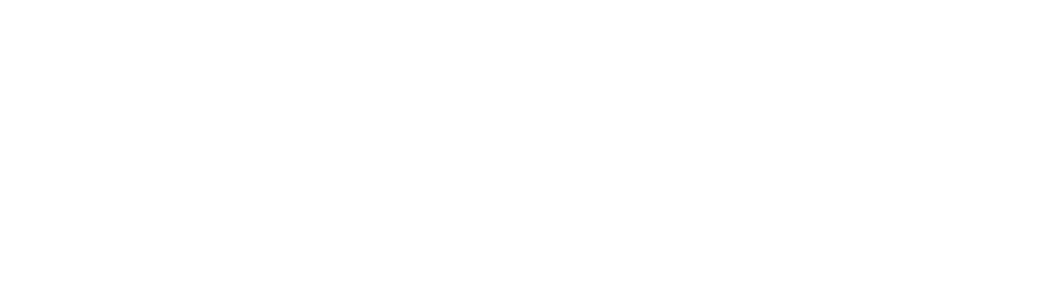~第10回~ 検査のアレコレ!
突然ですがみなさん。
このハエの写真をみたことはありますか?

小さい頃から眼科に通っていた方は、もしかしたら見たことがあるかもしれません!
この本は、偏光メガネというサングラスのようなものを掛けてみることによって、ハエの羽が浮き出て見える本です。
また左のページ上部の4つの丸が9つありますが、1つだけ浮いて見えるようにもなっています。
さらに下部は、A・B・Cの列それぞれに一匹だけ浮いている動物があります。
視差といって、飛び出し具合が少しずつ変わっていて左の9番の丸が一番難しいです。
右ページの一番下にRとLが書いてあります。
片眼ずつで見てみましょう。


右眼で見たときはLが薄くなり、左眼で見たときはRが薄くなります。
どちらの眼で見ているのかが一目瞭然です。(これは利き目の検査ではありません)
これは両眼視機能検査にあたります。
簡単に言えば両眼を使ってものを見ることができているのか、どのレベルまで見えているのかを調べる検査です。
大体3歳くらいからできるようになります。
両眼視機能検査はまだまだあります。
低年齢でできる器具はこちら、「輪通し法」といいます。

カギがついている方を患者さんに持ってもらい、丸が両端についている方を検者が持ちます。
うまく穴にカギを入れることができれば大まかな立体視があることが確認できます。
指が上手に使えるようになる2〜3歳くらいでできるようになります。
ひとえに検査と言っても、たくさんの検査がありますので
ぜひオープンキャンパスなどで試してみてくださいね!☺